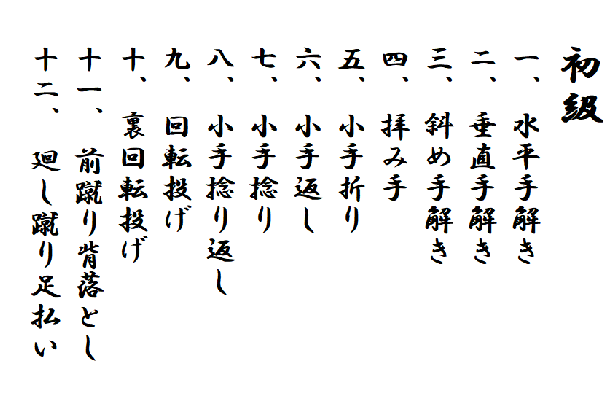| 物外は文政四年(一八二一)の冬、周防の瑠璃光寺に入って立身し(僧位を取った)、 翌五年、二十九歳のとき広島の伝福寺に帰省したが、天保元年(一八三0)、四十歳ち かくなって尾道の済法寺の住職になった。 道場を建てて門人を教えたのは、それ以降である。一説には、道場を建てたのでなく、 庫裏を道場にしたともいう。 大力の逸話は広島方面にも多くのこった。 天保年中に大日照りがあった。 「物外さん。こう雨が降らんでは百姓は日干しになります。雨乞いしてくださらんか」 農民どもの願いである。和尚、人工降雨術のほうは得手でないが、頼まれては引受け ざるを得ない。 「よし。きくか、きかんか、やってみよう」 ところで、そのやり方が変わっていた。 済法寺の鐘をはずして吉和村の海岸にかつぎ出し、二隻の船のあいだに繋いでこれ を海上にうかべ、十七日のあいだ昼夜を分かたず祈願した上で、こんどは褌ひとつにな って鐘の竜頭に手をかけ、大喝一声、二、三間も遠くの沖へ投げ込んだ。 何しろ、百貫目以上あるという巨鐘をひとりで投げこんだのだから、これには八大竜王 もびっくりしたに違いない。たちまち霊験があって、沛然と雨がふりだした。 「物外さんの雨乞いは、きき目があるのう」 ということになり、それからも日照りがあるたびに、物外に雨乞いを頼むようになった。 海中に投げこまれた鐘はその後、漁師の網にかかってもどって来たが、鐘のイボが八 個欠けていた。八大竜王が一個ずつ受納されたのだろう、と物外さん、うまい解釈で信 心家を感心させたものだ。 市内の海蔵寺で勧進相撲があった。大関の御用木(ごようぎ)というのが拳骨和尚のう わさを聞き、かげ口をきく。 「へん、力持ち、力持ちといったところで、たかがお坊さんの力じゃ知れたもんでごわん すな。はばかりながらこの御用木の大力といえば、そんな子どもだましじゃごっせん」 それをきいて知らせた者があるので、さすがの物外もちょっと腹にすえかねた。すぐに 海蔵寺へやって来て、御用木に言った。 「おまえさん、たいへんお強いそうだのう。どうだろう、拙僧の拳骨を、おまえさんの頭で 受けることができるじゃろうか」 「できるとも。やって見なさるがようござんすわい」 しかし、そばにいる人たちが心配した。 「物外さんの拳骨を頭で受けるなんて、とんでもないことだ。やめさっしゃれ」 「そんなに強いのか」 御用木、ちょっと心配になる。 「強いとも強いとも。そなたの頭が割れるのは必定じゃよ」 「ふうん・・・」 語尾がすこしふるえる。いまさら止めるとも言いかねて、もじもじしていると、 「決心がにぶったらしいのう。拙僧は何も、おまえさんの頭でなくちゃならんというわけ ではないよ」 ちょうど側にある海蔵寺の門柱をぐわーん、と一発くらわした。 そこだけポコンと、へこんだ。その痕が戦前までのこっていたが、大戦の原爆投下で吹 っ飛んでしまった。 天保十五年(十二月改元、弘化元年)五十一歳。済法寺で江湖会を修す。 嘉永元年(一八四八)、物外五十九歳。文人画の名手として知られた貫名海屋(ぬきな かいおく)が京から下り、物外を訪問して力業を見せてもらいたいと頼んだ。 物外は寺のうらの竹林に入り、素手でその枝葉をしごきおとし、指先でひしいで襷にし 門人と剣術をして見せた。何人かに勝ち抜いてから、こんどは四人の相撲取に船の艫 綱を持たせ、それを物外の腰に巻き付けて、四人で力限りに引っ張らせたけれど、物外 は大盤石のごとくでビクともしなかった。 済法寺のうらに大きな石があった。厚さ一尺五寸、長さ一間以上、これを六人の人夫 がかついで門前へ移そうとして、大いに手こずっている。するとそこへ物外さんが、のこ のこ出てきた。 「何だ、まだぐずぐずやっているのかい。よしよし、おれにまかせろ」 物外は人夫たちを押しのけ、そばにひろげてある菰のうえにその大石を抱きあげたと 思うと、手ばやく菰につつんで持ち上げた。 「玄関へすえればいいのだな。そこをのいてくれ。歩くのにじゃまだよ」 すたこら運んで行ってしまう。 同じ嘉永元年三月のころ、九州から武者修行者が済法寺へやってきた。和尚に対面 してお茶を喫んでから、しばらく雑談をしていたが、突如手にした茶飲み茶碗を鷲づかみ にして、ミリリッといわせて砕いてしまった。 物外、顔色も変えないが、こころの中では、こやつは力のあるのを自慢で無礼なまね をしやがる、と思ったから、自分の持っている茶飲み茶碗を三本の指で三べんキリッとま わしてから、指先だけで微塵に砕いて見せたので、武士は自慢の鼻を折られ、会話をそ こそこにして辞去して行った。 あるとき備中岡田の藩士、身のたけ七尺もある豪男の武士が、物外和尚と力くらべし たいといって訪問した。それでは、と物外は寺のうしろの山から二十貫目余りもある、餅 搗き臼に似た丸石を小脇に抱き、片手で数珠をつまぐりながら帰って来たので、武士は 肝をつぶし、ほうほうの態で逃げ去った。 |
|
|